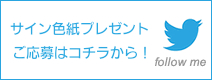―― ミニアルバムのタイトル『HeartBreak』という言葉にはどのようにたどり着いたのでしょうか。
いつもアルバムタイトルは、できあがった曲たちを並べてみて、それらを形容するのにもっともふさわしい言葉を考えて決めてきました。今作は初めて、自分が失ったものや自分のもとから離れてしまったひとに対して歌ってみようと思って作った曲ばかりで。あと、自分自身と向き合っていく上で、ずっと抱えたままの諦観、鬱屈とした気持ちも表れていて。
さらに、収録曲を作っていた時期にもっとも聴いていたのが、WEEZERの「Say It Ain't So」という楽曲でして。その歌詞に<heartbreaker>というワードが出てくるんです。その響きがカッコよくて好きで。まさに自分の気持ちや生き方、今作の収録曲たちにリンクするなと『HeartBreak』と名づけました。
―― もっとも今作の核になったと思う楽曲というと?
いちばん最初に制作した「サンバースト」ですね。すでにシングルリリースされているこの曲が軸にあったからこそ、今後どんな挑戦をしても自分はブレないと感じられて、アルバムを作り上げていくことができたのだと思います。
―― 「サンバースト」はどんなきっかけから生まれたのですか?
"Serotonin tour 2024"を行なっているときから、自分たちの立ち位置や規模感についてずっと考え続けていたんです。フェス出演や大きなステージに立つ機会が増えて、まわりから「調子がよさそうだね」とか「売れたね」とか言われることが多くなりました。古い友人から連絡が来て、「○○に出るんだって? すごいじゃん! まさか俺の友だちがこんなふうになるなんて」と言ってくれたりもして。もちろんそれは嬉しく思います。
ただ自分としては、そういう変化の実感はあまりなく、あくまで淡々と延長線上で活動している感覚が強くて。だからこそ、「自分たちは見合ったことができているのか?」という疑問が常にある。そもそも、大きいステージに立つことや、大勢に聴いてもらえることが、音楽的にいいことなのか。その基準すら僕はひとと違うのかもしれません。「自分はこんなもんじゃない」とか「もっとこうしたい」みたいな気持ちもありますし。
そんななか、10年前から自分が憧れていたような先輩アーティストの方々と、同じステージに立たせていただいたり、ツアーに呼んでいただいたりして。そこで彼らの姿を観たとき、「ああ、やっぱりカッコいいな」って。
―― 歌詞に綴られている<何か一つも掴めない私が伸ばした 手を握るあなたの奥のあの太陽が 今も光っている>という状態ですね。
そうそう、「僕が本当になりたかったのは、こういう光だったな」ってしんみりしてしまうというか、改めて噛みしめるというか。そんな憧れに対する気持ちから生まれたのが「サンバースト」ですね。
―― <映った鏡の水面から 抜け出せなくて泣いている>、または<その下に映る水面から こっちを見てさ、笑ってる>のは、描いていたのとは違う自分自身のような感覚でしょうか。
まさに。音楽は本質を伝えるのがとても難しい表現であり、聴く側のバイアスにも大きく左右されるじゃないですか。僕自身も他のアーティストの楽曲を聴いて「思い込んでいた音楽」と「実際の音楽」のギャップに驚くことがありますし。シンガーズハイがそういう誤解を受けてしまうもどかしさをかなり感じています。
そもそもロックフェスのようなキラキラ華やかな場所が、僕はそんなに得意ではなかったのかもしれません。どちらかというと、アンダーグラウンドやライブハウスで鳴っている、鬱屈とした音楽に惹かれていた側で。じゃあ、今の時代の僕みたいなひとに、シンガーズハイの音楽を好いてもらっているのか。そう考えると、「きっと違うだろうな」と悔しくなるんですよね。
―― その葛藤は<どんな顔してたっけ どんな向きで合わせりゃ元に戻るんだっけ>というフレーズにも表れていますね。
しかもリリースをして自分の手を離れた瞬間に、曲は受け手のものになるわけで。それがどう受け取られるか、まったく想像できない。迷子のようになってしまう。とはいえ、どういった形でも自分たちの曲を「好き」だと言ってくれるひとたちはありがたいんですよ。だから、そういうひとたちを含めて、曲を自分の子どもであるような見方をしてしまうところがありますね。
―― その聴き手に対する愛情は、「サンバースト」の<いつかあなたが幸せになれる 世界を作ってみせるから>というフレーズや、「薄っぺらい愛を込めて」の<この世界を変えてみたいよ あなただけの思い通りに>というフレーズに滲んでいます。
1アーティストもひとつの文化になり得ると思うんですよ。自分たちをフックアップしてくれるひとが増えれば、結果的に「世界を作る」「世界を変える」と同義なのかもしれないなと。そう信じたくなるときがあるんです。「サンバースト」の<Everything's gonna be alright.>というワンフレーズにしても、僕らが祈りとして唱え続ける行為自体に意味があるなと思いますし。それぐらいの気概は持っていたいですね。
―― 1曲目「燁」も「サンバースト」と同じく“火”の熱を感じる楽曲です。
こちらの火は、もう少し弱々しくて、線香花火が散っていくようなニュアンスですね。僕、そうは見えないと思うんですけど、夏が好きなんですよ(笑)。夏って心が元気になるから。この季節からパッと思い浮かぶイメージや映像を曲にしてみました。あと、必ずしも失ったものを「人」で捉えるべきではないかもしれないと思って、自分の魂や感情を表せるようにあえて<火と>と表記してみたり。
―― さらに、2曲目「Youth」の<燃やした筈のあのギター>や3曲目「延長戦」の<夜空の向こう、見上げた花火>にも“火”が登場しますね。
たしかに! そこはまったく意識していませんでした。夏好きが出てしまいました(笑)。ちなみに<燃やした筈のあのギター>って実体験なんですよ。上京前、バンドを辞める最後のライブで、ギターをへし折ってしまいまして。売るに売れないし、直すくらいなら新品を買ったほうがいいし、困っていたら友だちが、「じゃあ、それ燃やしちまおうぜ」って。学生で若かったこともあり、ノリで本当に燃やしたんですよね。
―― そんな若かりし思い出もあっての「Youth」というタイトルに。
僕は小さい頃からずっとひとりでいたけれど、音楽を始めて変わりました。とくに上京前は、変に先のことを考えずにただ楽しんでいた、まさに“青春”と呼べる時期だったのかもしれないなと思ったんです。あと「Youth」は、そういう若い勢いがあるからこそ、最後に<離さないよ 愛してるよ>と言い切る強さも大事にして書きましたね。