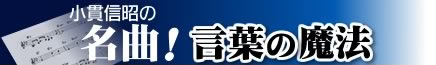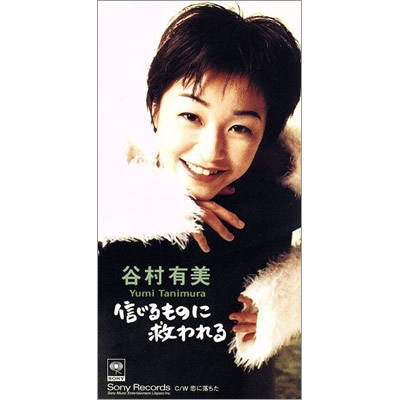かつて音楽雑誌が盛り上がっていた頃、そのなかのひとつに『GiRL POP』というのがあった(1992年の創刊)。当時、僕も執筆者としてお世話になったが、やがてこの雑誌名は「ガール・ポップ」という音楽ジャンルとして定着していく。今回、取り上げる谷村有美。他には永井真理子、森高千里などが、その代表格と言われた。
でも、「ホントのところガール・ポップって具体的にはどういうものなの?」と訊かれたら、即答は難しいのである。ひとつの雑誌が生み出した概念であるのは確かなので、「あの雑誌が取り上げていた女性アーティスト=ガール・ボップ」と言っておくのが無難そうだ。
“ガールズ・ポップ”と十把一絡げなのではなく、単数であることは示唆的だ。取り上げた人達は「個」で勝負していた(したいと思っていた)わけで、実際、彼女たちは単にボーカリストだっただけではなく、自作自演傾向も強かったのである。
さらに言うと、あの頃は若い女性の芸能形態として「アイドル」があり、その一方で女性の「ロック」も珍しくはなかったけど、本来は真ん中に位置すべき「ポップ」が人々の意識から抜け落ちぎみだった。
その大切な受け皿となったのが、ガール・ポップという音楽ジャンルだったのだ。あの雑誌の立役者である元編集者の前田くん、元気かなぁ(これは私信でした、スミマセン)。
さて、ジャンルの説明が長くなったが、谷村有美である。彼女はここ最近、再評価が著しく、デビューからの諸作が最新リマスタリングで再発され、好評を博している。メディアへの登場も多いようだ。
そもそも彼女のレコーディングには一流のスタジオ・ミュージシャンがこぞって参加しており、海外における日本のシティ・ポップ・ブームの流れのなかでも、そうしたファンの耳にかなう出来ばえのものが多い。つまり、リマスタリングする価値あるものが多く残されているということだ。
彼女のバイオ・インタビューを読むと、幼少期からピアノを習い、学生時代はフュージョン・バンドで腕を鳴らしていたそうなので、ミュージシャン指向が強かっただろうし、当時はレコーディング・スタジオに通うのが、さぞ楽しかったことだろう。で、このあたりのことをもっと書きたいけど、本コラムは歌詞に特化したものなので、いつもどおり進めさせていただく。
でも、「ホントのところガール・ポップって具体的にはどういうものなの?」と訊かれたら、即答は難しいのである。ひとつの雑誌が生み出した概念であるのは確かなので、「あの雑誌が取り上げていた女性アーティスト=ガール・ボップ」と言っておくのが無難そうだ。
“ガールズ・ポップ”と十把一絡げなのではなく、単数であることは示唆的だ。取り上げた人達は「個」で勝負していた(したいと思っていた)わけで、実際、彼女たちは単にボーカリストだっただけではなく、自作自演傾向も強かったのである。
さらに言うと、あの頃は若い女性の芸能形態として「アイドル」があり、その一方で女性の「ロック」も珍しくはなかったけど、本来は真ん中に位置すべき「ポップ」が人々の意識から抜け落ちぎみだった。
その大切な受け皿となったのが、ガール・ポップという音楽ジャンルだったのだ。あの雑誌の立役者である元編集者の前田くん、元気かなぁ(これは私信でした、スミマセン)。
さて、ジャンルの説明が長くなったが、谷村有美である。彼女はここ最近、再評価が著しく、デビューからの諸作が最新リマスタリングで再発され、好評を博している。メディアへの登場も多いようだ。
そもそも彼女のレコーディングには一流のスタジオ・ミュージシャンがこぞって参加しており、海外における日本のシティ・ポップ・ブームの流れのなかでも、そうしたファンの耳にかなう出来ばえのものが多い。つまり、リマスタリングする価値あるものが多く残されているということだ。
彼女のバイオ・インタビューを読むと、幼少期からピアノを習い、学生時代はフュージョン・バンドで腕を鳴らしていたそうなので、ミュージシャン指向が強かっただろうし、当時はレコーディング・スタジオに通うのが、さぞ楽しかったことだろう。で、このあたりのことをもっと書きたいけど、本コラムは歌詞に特化したものなので、いつもどおり進めさせていただく。
 1991年5月15日発売
1991年5月15日発売
まずは自著のタイトルにもなっていたこの曲を
「愛は元気です。」(1991年)である。いや、このタイトルは今もぴかぴか光って眩しいくらいだ。作詞は本人ではなく、今井美樹や嵐の作品などで知られる戸沢暢美。ちなみにKANの「愛は勝つ」は前年のリリースだったのだが、歌のなかで“愛”という言葉を真正面から取り扱うというのは当時の風潮だったかもしれない。
歌詞全体を眺めると、いわゆる“応援・励ましソング”にカテゴライズされそうだ。「僕」は(遠く離れたところにいるであろう)「君」を励まそうと語りかけている。
キラーフレーズとしては、[いとしさは勇気さ]と[せつなさはステキさ]のふたつだろう。相手がそこには居ない状況だから芽生える感情“いとしさ”“せつなさ”に対して、続ける言葉は[勇気]と[ステキ]。まさにポジティヴな響きである。
で、誰もが一番知りたいのは、このことではなかろうか。なぜ「愛」は「元気」なのか。そこで重要になるのは、「僕」にとっての「愛」が、どういう性質のものなのかということだ。どうやら「君」との共作物だという意識が強いようなのである。これはもちろん素敵なことであり、歌のポイントともなる。
で、少なくとも半分を担っているであろう「僕」が「君」に対して「愛」の現状報告をしているのがこの歌なのだ。こう考えると、「愛は元気です。」という言葉が具体的に響いてくるのである。
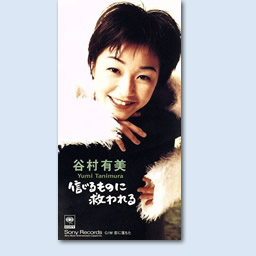 1995年2月22日発売
1995年2月22日発売
「は」と「に」の違いは大きいか?
次は「信じるものに救われる」である。こちらは作詞作曲とも谷村有美だ。この時代のJ-POPの嫌みのない前向きさが伝わってくる作品だ。
で、既にみなさんお気づきのとおり、ちょっとヒネリの効いたタイトルなのである。普段よく目にするのは、聖書に由来し、一般的な格言としても親しまれる“信じるものは救われる”だろう。しかしこの場合、あえて「は」でなく「に」になっており、ここに作者の意図が感じられる。さっそく細かくみていこう。
“嫌みのない前向きさ”と書いたが、ボーカリストである谷村有美の声質にも言えることだ。この歌のテーマはズバリこうである。大人になると無くしてしまいがちな[無邪気さ]や[夢を見る気持ち]は、むしろ大人になってからのほうが大切なのだと歌っている。
で、歌詞を目で追っていくと、さきほどの「は」と「に」のことが、より具体的に判ってくる。“信じるものは”ならば、明らかにこの“もの”は“者”のこと、そう、人物を指すだろう。しかし“信じるものに”となると、こちらの“もの”は先ほどの[無邪気さ]なりといった事象を指すことになる。平仮名ひとつで大きな違い。
さらに聴いていくと、タイトルから派生した言葉は[信じ続けるものは]へ発展していくのだった。もうそうなると、ここでの“もの”は事象じゃなく人物を指す“者”ということになる。
そしてそしてラストの一行だ。ふたたびツイストが効いている。最後の最後は[信じ続けたもの]に[きっと救われる]と結んでいるのだが、ここでは“者”じゃなく事象を指す“もの”へ戻っている。こういう書き方するとややこしいが、そんな細かな言葉遊びも冴えてる作品なのだった。
筆を置く前に、自分の胸に訊いてみた。果たした僕は、“信じるものに救われ”た経験があっただろうか?
いや、あった筈である。具体的には言えないんだけど…。
小貫信昭の名曲!言葉の魔法 Back Number
近況報告 小貫 信昭
(おぬきのぶあき)
橋幸夫さんが亡くなった。この人の残した作品についてはリアル・タイムで知っているものと、音楽に凝りだしてから再発見したものと、ふたつの思い出がある。リアル・タイムでいえば、小学校の頃に流行っていた「霧氷」だ。でも、歌の出だしの“♪む~ひょう~ む~ひょう~”は、たんに音で覚えたので、それが“霧氷”だと知ったのは後からだった。二十代になり改めて発見したのは「あの娘と僕ースイム・スイム・スイムー」である。ちなみに“スイム”はサーフィンから派生した踊りのリズム。ロックっぽい作品だった。どちらも60年代中頃のリリースで、橋さんの名唱により支えられていた。
橋幸夫さんが亡くなった。この人の残した作品についてはリアル・タイムで知っているものと、音楽に凝りだしてから再発見したものと、ふたつの思い出がある。リアル・タイムでいえば、小学校の頃に流行っていた「霧氷」だ。でも、歌の出だしの“♪む~ひょう~ む~ひょう~”は、たんに音で覚えたので、それが“霧氷”だと知ったのは後からだった。二十代になり改めて発見したのは「あの娘と僕ースイム・スイム・スイムー」である。ちなみに“スイム”はサーフィンから派生した踊りのリズム。ロックっぽい作品だった。どちらも60年代中頃のリリースで、橋さんの名唱により支えられていた。