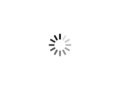幸せの猫
週末が来るたびに 彼女は華やいだ
私を抱き上げて 彼を待ちながら
「kis macska 世界一 素敵な仔猫」って
くしゃみが出るまで 頬ずりをする
足取りは ステップに
囁きは メロディーに
小さな部屋に 夕暮れは
いつでも 優しかった
階段を軋ませる 靴音がすると
私を肩に載せ チェーンを外した
「kis macska 御機嫌よう 可愛いおヒゲ」って
その人は恭しく 挨拶をする
ストーブは 赤く燃え
ケトルから 白い息
彼女の膝で うとうとと
二人の 声を聞いた
ああなのに今日だけは どこかが違ってた
いつもの時間を 時計が告げると
「kis macska じゃあまた」って 撫でてくれたけど
その手には知らない 匂いがあった
ゆっくりと ドアーの音
滑り込む 細い風
彼女は何も 気づかずに
笑顔で 私の手を振る
幸せは 一つなの
一つだけ あればいい
私と居れば 誰一人
もうすぐ 要らなくなるの
私を抱き上げて 彼を待ちながら
「kis macska 世界一 素敵な仔猫」って
くしゃみが出るまで 頬ずりをする
足取りは ステップに
囁きは メロディーに
小さな部屋に 夕暮れは
いつでも 優しかった
階段を軋ませる 靴音がすると
私を肩に載せ チェーンを外した
「kis macska 御機嫌よう 可愛いおヒゲ」って
その人は恭しく 挨拶をする
ストーブは 赤く燃え
ケトルから 白い息
彼女の膝で うとうとと
二人の 声を聞いた
ああなのに今日だけは どこかが違ってた
いつもの時間を 時計が告げると
「kis macska じゃあまた」って 撫でてくれたけど
その手には知らない 匂いがあった
ゆっくりと ドアーの音
滑り込む 細い風
彼女は何も 気づかずに
笑顔で 私の手を振る
幸せは 一つなの
一つだけ あればいい
私と居れば 誰一人
もうすぐ 要らなくなるの
RANKING
工藤順子の人気動画歌詞ランキング