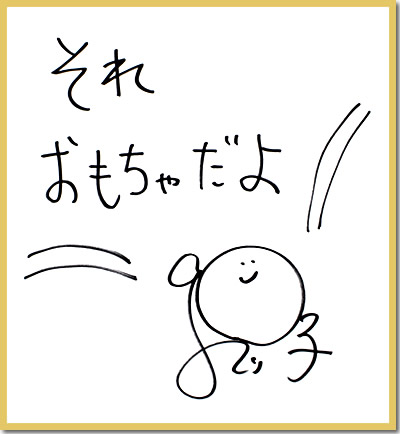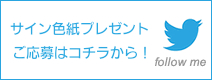―― ニューアルバム『街よ街よ』というタイトルには、どのようにたどり着いたのでしょうか。
すべての楽曲を録り終わって、最後に決めました。今回は収録曲に出てくる歌詞に特徴があって。たとえば多く出てくるのは<道>。「宝物を探して」の<地元の駅>、「踊り場」の<太陽>や<満月>や<屋上>、「人一人」の<海沿い>、あと「ホテル太平洋」も建物じゃないですか。そういうすべてのワードを足したら、ひとつの“街”ぐらいのサイズになるな、って気づいたんです。
このアルバムを聴いたら、ひとりひとり思い浮かぶ“街”が違うんだろうな、とも思って。そのひとの経験や想像力で作られる“街”がある。だから、それぞれの街に呼び掛けているようなイメージで『街よ街よ』という言葉にしました。
―― 街を描こう、と意識されたわけではなく、客観的に楽曲を眺めてみたら“街”だったんですね。
そう、こういう感じになるとは最後までまったく気づかずに。前作アルバム『日記を燃やして』の制作時、すでに在ったけど収録してなかった曲も、今回のタイミングで入れていますし。それこそ「慎重にならないか」なんて6年前の曲やし。かなりいろんな時期の楽曲が集合しているんです。
―― 3曲目「私はパイロット」で<飛行機>に乗り、4曲目で“離陸”して、5曲目「このよかぶれ」で<奇跡の惑星>に着地している流れなど、かなり物語を意図して楽曲を作られたのかと感じていました。
そうなんですよね。楽曲を作っている段階では無意識なのに。私はアルバム単位で聴くのが好きなんですよ。通して聴いたとき、ちゃんとひとつの作品にしたい。だからやっぱり今回もかなり曲順を大事にしました。それで「この曲のあとに、この曲が来たら、どっちもよりよく聴こえるな」という感覚で選んでいったら、物語ができていたというか。
―― 変な感想ですが…、「私はパイロット」に<人は宇宙で 私は宇宙人よ>というフレーズがありますよね。今回のアルバムはどこか全曲を通じて、絵莉子さんが<宇宙人>として街を眺めているような印象を受けました。
あはは! なるほど! いや、でもたしかに言われてみるとそういう面があるかもしれないです。実際に私は、ちょっと離れて楽曲を見てみたことで“街”だということに気づいたから。人間として歩いているだけだったらわからなかったけど、<宇宙人>の視点になって、初めて街のサイズがわかったというか。よく考えたら不思議と「このよかぶれ」というタイトルとかも宇宙人がつけたように思えてきました(笑)。
―― 1曲目「踊り場」もこのアルバムの入り口として素敵ですね。何階でもない場の自由さというか。
踊り場ってなんかワクワクしますよね。作ったときにはいつも通り、頭から歌詞を書いて、それに曲をつけたんですけど。できあがってみたとき、始まりの感じでもう「これはアルバムの1曲目にしよう」と決めていました。
―― どんな時に生まれた楽曲だったんですか。
曲をつけたのは一昨年の秋ぐらいかな。まさに「2ndアルバムを作り始めようかな」というタイミングでした。歌詞はそれよりも前に書いているから、ちょっと正確な時期は曖昧なんですけど。自分自身が来年40歳になるぞって時で。40歳って、フレッシュで若いわけではないけれど、すべてを知っている年齢でもない、ちょうど真ん中な年齢な気がして。それが「踊り場」っぽいなと思ったんですよね。そこから「踊り場」という曲を作ってみよう、と書き始めたのを覚えています。
―― 最後<ブルーハワイ>から<ストロベリー>に変わるのが好きです。楽し気な雰囲気から、きゅっと甘酸っぱく切なく終わりますね。
そうなんですよ。これ<ブルーハワイ>は夏のイメージなんです。そして<ストロベリー>は冬のイメージ。夏から冬に季節が変化する感覚を表してみました。
―― 2曲目「人一人」は、歌詞に<私>や<君>という人称がなく、1番に登場するのも<どっか>、<あの曲>、<あの話>と余白が多いのが印象的で。聴くひとがそれぞれのイメージをより膨らましやすい楽曲ですね。
今回のアルバムは無意識のうちにそういう楽曲が集まったんですけど、とくにこの曲はそうですね。これはコロナ禍に書いた歌詞で。あまり他者に接触してはいけない時期だったので、“一人、だけど一人じゃない”という不思議な感覚を表したかったんです。
―― 誰かに話したいのに話せない状況だったがゆえの、<どうしたらいいの でどうすんのこれ>というフレーズなのですね。
そうそう、「この話をどこに持っていけばいいのよ?」とか「会わないと始まらないのに」みたいな。そういうコロナ禍の本音が入っています。そして、結局2番では我慢できず<あの話>のネタバレを曲のなかで話しちゃうんですよね(笑)。
―― ちなみに、サビの部分はどうして<人>以外はひらがな表記なのでしょうか。
最初は漢字で書いていたんです。でもためしに全部をひらがなにしてみたら、<人>が際立って。しかも上手いこと、文字が綺麗に長方形に収まりまして。こういう表記にしてみました。
―― 絵莉子さんがこのアルバムでとくに思い入れの深い楽曲というと?
アルバムラストの「偏愛は純愛」ですかね。サビの<あの歌聴こえる 私の耳には あの歌聴こえる 私の耳だけには>というフレーズだけ、高校3年生のときに作ったもので。当時のAメロなどは変えて、新たに書いたんです。10代の頃に生まれたこのフレーズをいつか使いたいな、とずっと温めていたので、やっと叶ったなと。
―― 当時、高校3年生だった絵莉子さんはどんなことを考えてこのサビを書いたのでしょう。
受験期で、みんな塾に行って勉強をしている、そういう匂いや空気感のなかで書いたのを覚えています。「今までずっと同じようにひとつのクラスで過ごしてきたけど、それぞれ違うところへ行くんだ」という気持ちもあったし。あとなんか…「自分だけのものがあるはず」って思っていましたね。
―― 最後のサビ前にパッと入ってくる<それおもちゃだよ>というワードも気になります。
そこ、気になりますよね。そのもうひとつ前の<幼い頃の憂鬱が 今になって生きている>というフレーズと関係していて。子どもの頃、本物だと思って見ていたものを、大人から「それおもちゃやで」って言われて、「え…」って傷つくみたいなことありませんでした?
―― あー!
子どもってそれなりに精一杯、「自分は大人や」と思っているじゃないですか。でも「それおもちゃだよ」=「子どもだね」って言われた気がして。その“しゅん…”ってなる感覚を私ずっと覚えているんですよ。だから歌詞のなかでも、誰かから言われた「それおもちゃだよ」って言葉として存在している、という感覚ですね。
―― 誰にそう言われたとしても、「自分だけのものがあるはず」だと。
はい。「私にはわかる気がする」という強い気持ち。サビでその感じが伝わったらいいなと思いながら書きました。「偏愛は純愛」というタイトルも、サビをタイトルにしたようなものなんですよね。「私だけの“好き”は純度100%だよ」って言いたかったんです。