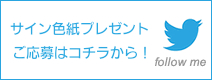―― 収録曲のなかでもとくに「It rains」はよりメッセージ性の強い楽曲ですが、これはどのように生まれたのでしょうか。
KUMI これはまさにNAOKIが、「俺が書いてみたい」ってほぼ全編書いたよね。ボブディランの世界というか。
NAOKI そう。オケもボブディランを意識していて、他の曲に比べるとドラムやベースがすごく小さくて、KUMIの歌とアコースティックギターが大きい、ちょっと変わったバランスのミックスで。今、世の中が、ちょっとね。ロシアによるウクライナ侵攻のことで…。その場にいないのでこれ以上深いことは無責任に書けないけど、泣きながら作ったよ(笑)。
―― 歌詞は、何かを批判しているわけじゃなく、真実だけが書かれている印象を受けました。
NAOKI そういう感じにしたかったんだよ、ありがとう。伝わっていて嬉しいよ。少しでも多くのひとが、イマジネーションする機会を音楽って与えてくれるから。
KUMI 本当に戦争って意味ないよね、ってことがこれを聴けばわかる。誰も幸せにならないよねって。
NAOKI ね。でも音楽家でよかったなって思うのは、そういう重い言葉をときにはライトにメロディーに乗せて伝えられるところなんだよね。やっぱりユーモアも交えて、歌詞だったら銃弾を<drumroll>ってワードで包んだり。言葉だけでディスカッションしたり、訴えを起こしたり、もちろんその役割をやらなきゃいけないひとたちも、苦労も知っているけれど。歌はもっと違う角度で、イマジネーションだけみんなの血肉にしていけるじゃない。今だって、新聞の取材じゃないのにこういう話ができる。音楽って人類の必殺技だと思うんだよね。
KUMI そういうことだよね。芸術は魂に響くからね。
NAOKI しかも国会議事堂の前で険しい顔して歌うわけじゃなく、ポップミュージックとして街のなかで奏でることができる。で、奏でるにあたって、批判じゃなく、「事実を記すだけにしよう」って思って書いたんだよ。だからそこが伝わっていて嬉しい。
―― では、おふたりがこのアルバム収録曲のなかでとくに好きなフレーズを教えてください。
KUMI パッと出てくる?
NAOKI 「A revolution」の<10 to nothing, weʼre behind>かな。
KUMI あれはうまくハマったね。パンチがあるね。
NAOKI 今僕らは10:0で負けているかもしれないけれど、でもこれが終わりじゃないって。ヘヴィーなギターに乗っけて、そういうことを叫んでいるのが俺は好きだな。
KUMI いいね、いいと思う。
NAOKI <ペパロニカーペット>も好きなんだけどね(笑)。
KUMI これは伝わるかわからないんですけど、「Hallelujah to you」の<答え探した days>と<君を探す today>はメロディーと相まって好きですね。答えがないのに一生懸命探している憤りをうまく表現できたかなって。報われない感じ。
NAOKI マニアックに来たねぇ。
―― ちなみにHallelujah(ハレルヤ)とはよく聞くワードではありますが、具体的にはどんな意味合いを持つのでしょうか。
KUMI <Hallelujah>ってキリスト教で、神を称えるような言葉だけど、たしかに何が語源なんだろうね。だから「Hallelujah to you」ってキリスト教徒のひとには、どう受け取られるんだろうなとも思う。<Hallelujah>という言葉の響きとイメージを自分で解釈して使っているけれども。
NAOKI 宗教的な意味合いはまったくないね。「君に幸あれ」ぐらいなニュアンスかな。
―― 曲のなかで聴くとおまじないのように響きますね。
KUMI そうだね。カタカナにしても<ハレルヤ>ってなんかパワーのある言葉じゃないですか。文字面もいいし。好きな響きでカジュアルに使わせてもらったよね。
NAOKI あとは改めて俺さ、やっぱり「Swingin'」の歌詞も好きだな。
―― わたしも好きです。とくに<幸い何気に手が触れるくらいで..You and I>のフレーズ力といいますか。
NAOKI そうそう、言い回しの妙というかね。まさに同じところで<案外無邪気に笑ってるくらいが real>とか<大抵少しの想い揺れるくらいで tears>とか、ここらへんすごく好き。
KUMI メロディーと相まってね。そういえば「Swingin’」は、とくに日本語がよく聴こえる歌詞にしたいっていうのもあったね。だから言い回しが可愛らしく転がっている感じがする。
NAOKI カジュアルで昔のコバルト文庫みたいでいいでしょ(笑)。日本語って可愛いなって思う。
KUMI あと私は「Radio song」のサビも好きかな。<君に触れた隙間から溢れ出す music and love>って、よくわからないんだけど(笑)。でも歌で聴いていると、ハッって。音楽を聴いているときに自分がぶわぁ…!ってなるあの感覚がちゃんと蘇るの。
―― おふたりは歌詞にあまり使わない言葉ってありますか?
NAOKI あー、あるよね。でもなんだろう…。
―― <あなた>とかも少ない気がします。
KUMI たしかに<あなた>使わないね!
NAOKI 使わないかな…。本当だ、使わないね。
KUMI 大体<君>だと思う。
NAOKI 響きもそうだし、<あなた>という言葉を使う主人公のキャラクターと距離感が自分たちのイメージにないからかもしれない。
KUMI そうだね。言葉の持つ重さというか、イメージというか。<君>って、性別もあまり特定されない軽やかさがあるから。意外とそういうところもLOVE PSYCHEDELICOの歌詞では大事なのかもしれない。
―― ありがとうございます。では最後に、おふたりにとって歌詞とはどういう存在でしょうか。
KUMI うーん。
NAOKI いろんな楽器があるけどさ、声だけはみんなが持っている楽器じゃん。だからいちばん共感できるのって、歌であり、歌詞だと思うんだよね。俺、今回のアルバムでも歌詞のない「Good bye moon」とか、毎回聴くかわからないもん(笑)。歌詞は、人間の日常に一番近い楽器であり、音楽の世界の中心だと思っているかな。
KUMI 中心かぁ。「歌詞が何か」はうまく定義できないけど、作詞が曲作りでいちばん大変な作業で。よく「歌なんかなければいいのに」って思うんだけど…。
NAOKI 俺と逆じゃん!

KUMI 曲ばかり作っていたいって。そのほうが自由度は高いし、ずっと心地よくいられるのに、パーっと広がるイマジネーションや伝えたいエネルギーを、「歌詞にしなきゃ」って瞬間にすごく制限される。狭いところにくる感覚があるんだよね。でも、だからこそ言葉や歌があると伝わるのかもしれない。大事だと思う。
NAOKI あとさ、もともとこういうポップスのロックって、日本で生まれたものじゃないじゃん?
KUMI それもあるね。日本語との相性ね。自分の好きな西洋の音楽のグルーヴやメロディーに日本語を乗せる不自由さはずっとある。
NAOKI そう。そして日本の場合、僕ら表現者にとって、音楽に日本語をどう乗っけるかってことがひとつ、哲学の答えみたいになっているんだよね。
KUMI うん、なっちゃってるね。
NAOKI 「このひとはこういうロックにどうやって日本語を乗っけるんだろう」っていう日本の音楽の楽しみ方がある。10人いたら10人絶対に乗っけ方が違って、そこに哲学があるから、聴いていておもしろいなと思う。
―― おふたりもずっと日本語を諦めてないですよね。だからこそ日本語と英語とをうまく融合されている。
KUMI そう、切り離せないんだよ。やっぱり日本人だからね。日本語好きだし。
NAOKI そういう日本で音楽をやっている楽しさってあるよね。
KUMI …大変さとね(笑)。