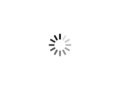グッバイ・マイマリー
都会の乗り換えも慣れた六月の正午
下品な中吊り広告を
ボーッとただ流し込んでいた
駅から二分 自動施錠のワンルーム
君が茹で上げたパスタは
いつも決まって柔らかいけれど好きだ
二人でよく行った五百円の飲み放題
薄めで頼んだレモンハイ
たった二杯でほっぺ赤った
酔っ払った君は特に可愛かった
デザートは酒肴になるんだって
得意げに二つ頼んでた
首都高は僕らに見向きもせずに流れて
同じように季節も流れてた
結婚したいなって思ってたんだ
でも思っていただけだったんだ
どういうことかわかんなかった
合鍵で開けても君はいなかった
僕の荷物がまとまり 手紙が置いてあった
どうしたらよかった?
そんなこと僕はわかってた
君がくれたリュックを背負ってた
寝る前に必ず化粧を落としてた君のことだ
しっかりごっそり僕のことも
キレイに落として寝ているんだろう
ストローを噛むようにイライラしてばっかりの
僕の小ささが僕を見離した
結果次第だって思ってたんだ
あと一年で変わってたんだ
どうしたらいいかわかんなかった
合鍵で開けても君はいなかった
「なんちゃって」って出てくる気がしてやまなかった
僕が写真を眺めてる間に
君は結婚しちゃったりするんだろうか
隣になぜか花束とタキシードでキメ込んだ
僕がいるんじゃないかって思ってしまっている
ちゃんとしようって思ってたんだ
でも思っていただけだったんだ
どういうことかわかってたんだ
合鍵をポストに入れて去ったんだ
頑張れと書かれた手紙は持って帰らなかった
結婚したいなって思ってたんだ
でも思っていただけだったんだ
どういうことかわかんなかった
合鍵で開けても君はいなかった
僕の荷物がまとまり 手紙が置いてあった
下品な中吊り広告を
ボーッとただ流し込んでいた
駅から二分 自動施錠のワンルーム
君が茹で上げたパスタは
いつも決まって柔らかいけれど好きだ
二人でよく行った五百円の飲み放題
薄めで頼んだレモンハイ
たった二杯でほっぺ赤った
酔っ払った君は特に可愛かった
デザートは酒肴になるんだって
得意げに二つ頼んでた
首都高は僕らに見向きもせずに流れて
同じように季節も流れてた
結婚したいなって思ってたんだ
でも思っていただけだったんだ
どういうことかわかんなかった
合鍵で開けても君はいなかった
僕の荷物がまとまり 手紙が置いてあった
どうしたらよかった?
そんなこと僕はわかってた
君がくれたリュックを背負ってた
寝る前に必ず化粧を落としてた君のことだ
しっかりごっそり僕のことも
キレイに落として寝ているんだろう
ストローを噛むようにイライラしてばっかりの
僕の小ささが僕を見離した
結果次第だって思ってたんだ
あと一年で変わってたんだ
どうしたらいいかわかんなかった
合鍵で開けても君はいなかった
「なんちゃって」って出てくる気がしてやまなかった
僕が写真を眺めてる間に
君は結婚しちゃったりするんだろうか
隣になぜか花束とタキシードでキメ込んだ
僕がいるんじゃないかって思ってしまっている
ちゃんとしようって思ってたんだ
でも思っていただけだったんだ
どういうことかわかってたんだ
合鍵をポストに入れて去ったんだ
頑張れと書かれた手紙は持って帰らなかった
結婚したいなって思ってたんだ
でも思っていただけだったんだ
どういうことかわかんなかった
合鍵で開けても君はいなかった
僕の荷物がまとまり 手紙が置いてあった
RANKING
My Hair is Badの人気動画歌詞ランキング

![[TAB] グッバイ・マイマリー / My Hair is Bad ギター](https://i.ytimg.com/vi/9V4fG9rHKu4/default.jpg)